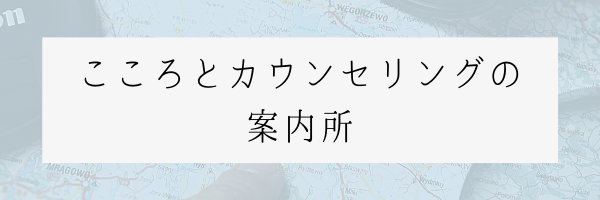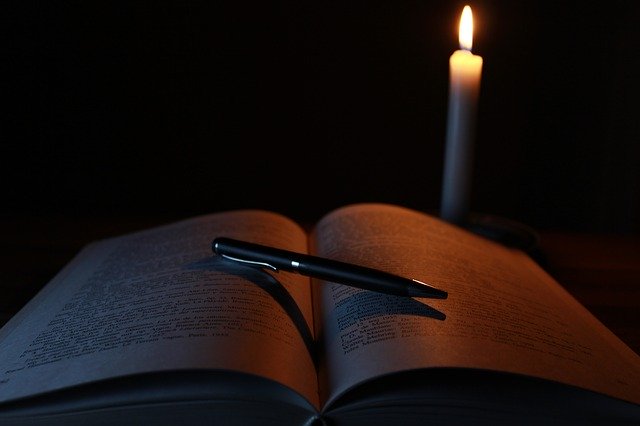
ジブリ作品が映画館で上映され、かなりの数の観客を動員しているというニュースをみました。上映されている作品は、『風の谷のナウシカ』『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』『ゲド戦記』の4本のようです。
この中の1つである『ゲド戦記』には、原作でも映画版でも物語のキーとして「真の名(まことのな)」というものが出てきます。
「真の名」というのは、『ゲド戦記』の世界において、太古の時代からこの世の全てのもの1つ1つに定められているもので、魔法使いはこの「真の名」を知ることで対象を支配し操ることができるとされています。そのため、人々は普段は「通り名」を使い、「真の名」は信頼できる人以外には知られないようにしています。
こういった、「名前」を知ることでその対象を支配する、という構図はファンタジーの物語によく出てきます。
同じくジブリ映画の『千と千尋の神隠し』でも、湯婆婆という魔女は名前を奪うことで相手を支配していましたし、ファンタジー児童文学として有名なミヒャエル・エンデによる『はてしない物語』では「名前を与えること」が物語の1つのキーとなっています。西洋ファンタジーだけではありません。夢枕獏による『陰陽師』では安倍晴明が「眼に見えぬものさえ、名という呪で縛ることができる」と語っています。
*
これと同じことが人の心に関しても言えます。それは、心のモヤモヤや感情に「名前」がつくとそれらを扱いやすくなる、ということです。
「名前」があるということは、他のものとは「別の存在」であるということの証です。逆にいえば、私たちは対象に「名前」をつけることで初めて、それを有象無象の世界から1つのまとまりとして浮き上がらせ、自分とは「別の存在」として扱えるものにするのです。
エスキモーの言葉には「雪」の種類を表す「名前」が何十個もある、といわれています。それは言葉の違いではなく、認識の違いです。エスキモーには容易に見分けられる「雪」の種類であっても、その「名前」を知らない人間が「雪」の違いを区別をすることは難しいでしょう。
このように「名前」は、世界からある「現象」を切り取って区別し、取り扱えるようにするという重要な役割をもちます。
*
心のモヤモヤやうまく言葉にならない感覚や感情。そういったものに「名前」がつくと、私たちはそれらから距離をとることができ、それらについて考えることが出来るようになります。
その「名前」は「哀しみ」や「怒り」かもしれないし、「誰かにすがりつきたくなるような心もとなさ」「誰かが去って1人ぼっちになる恐怖」かもしれません。どんな「真の名」がつくのかは人によってそれぞれ異なるのでしょう。
いずれにしても、名づけられる前はモヤモヤと自分は混然一体で、むしろ自分がモヤモヤに支配されているような状態であったのが、それに「名前」がつけられ自分とは「別の存在」として切り離されることで、私たちはようやくそれについて考えられるようになります。その輪郭をなぞり、その性質を知り、それが一体どこから来たのか、何を意味しているのか、どういう役割があったのか、などについて検討できるようになるのです。
言葉や「名づけ」がもつ力というのはとても強く、時には、逆に自らを縛ってしまうこともあります。しかし、同時に「名づけ」は、私たちが自らの心について考えるための強力な手がかりにもなってくれます。私たちは残念ながらゲドのように魔法は使えませんが、この「名づけ」の力というものは、世界や自分についての認識を変化させるという点において、人間に与えられた一種の魔法のようなものなのかもしれません。
<参考>