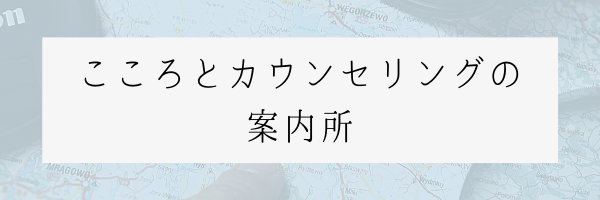哲学者の宮野真生子さんと人類学者である磯野真穂さんによる往復書簡『急に具合が悪くなる』を読みました。
宮野さんはガンを患っており、この往復書簡のやりとりの間に、実際に「急に具合が悪くなる」事態が生じています。全編を通して、迫りくる死をみつめながらも言葉を紡ぎつづける宮野さんの哲学者としての矜持と業が圧巻ですが、その宮野さんに対峙しつづける磯野さんの率直で真摯な態度もまた迫力に満ちています。そこには学問に従事する者としての決意と覚悟が感じられました。
*
お2人のやり取りには「固定され動きのないもの」と「動き続けること」の対比が形を変えて繰り返し出てきます。そして、私たちの生において後者の「動き続けること」がいかに大事であるかということも繰り返し語られています。「動き続けること」というのは先を予測できない不安定さや不安に満ちていますが、新しいものが生み出されるのはこの「動き続けること」の先にしかないのだということが、お二人のやりとりを通してまざまざと実感されました。
2人が直面している「死」というものはまさに「固定され動きのないもの」の最たるものと言えるのでしょう。「死」そのものが「動きのないもの」であるだけではなく、「死」を意識することもまた「固定され動きのない」状態を引き起こします。ガンのように「死」を意識せざるをえない病にかかると、その人の生活や内面が病(死)の視点に覆いつくされていく様が本の中にも描写されていました。それは、肉体的な動きを失うという物理的な「死」に至る前に、日々における外的・内的な「動き」が先に死んでいく事態ともいえるかもしれません。
この書簡は、そんな「死」を目前にし「動き」が取れなくなってしまうことに抗い、死が実際に訪れる直前まで動き続け生ききるという感覚を手放さないようにするための取り組みのようでした。
これはお二人の対話という形だったからこそ、成し得たことなのだろうと思います。
対話には他者が必要です。そして他者というのは未知のものです。私たちはともすると他者の言動を予測したり把握したりできるような錯覚を抱きますが、本来、他者というものは自分にとって予測不能で新しい動きを運んでくるものです。他者、そして他者との対話という未知に開かれることこそが、「死」のような「動き」がなくなっていく事態に、予測できない新しい動きを呼び込むことが出来るのかもしれません。そして、宮野さんにとってそれは磯野さんだったのだろうと感じました。
つねに不確定に時間が流れているなかで、誰かと出会ってしまうことの意味、そのおそろしさ、もちろん、そこから逃げることも出来る。なぜ、逃げないのか、そのなかで何を得てしまうのか、私と磯野さんは、折り合わされた細い糸をたぐるようにその出逢いの縁へとゆっくりと(ときに急ぎ足で)降りながら考えました。
*
「死」だけではなく、人生におけるその他の苦痛、苦悩というものもまた「固定され動きのない」状態を引き起こすのだと思います。苦痛や苦悩は、私たちを圧倒し、生活や内面をその苦しみで覆いつくし、私たちの外的・内的な動きを奪います。そして、その「動きのない」状態から抜け出すというのが1人ではなかなか困難なときもあるでしょう。
以前、『「他者に語る」ということ』というブログ記事に、カウンセリングにおける他者の必要性について書きましたが、カウンセリングというのは、苦痛や苦悩によって生じた「固定され動きのない」状態に、他者の存在を通して新しい動きをもたらすものなのかもしれない、とそんな風に思いました。
【引用】
・『急に具合が悪くなる』宮野真生子、磯野真穂(晶文社)